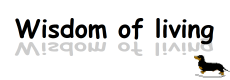スイカ
夏と言えばスイカ。スイカと言えば夏。
スイカ割り、スイカの早食い、種とばし・・・
夏の風物詩。スイカについて取り上げてみよう。
スイカとは?
スイカ(西瓜、学名: Citrullus lanatus「キトルルス・ラナツス」)
果実を食用にするために栽培されるウリ科の蔓(つる)性一年草。
原産は熱帯アフリカのサバンナ地帯や砂漠地帯。
日本に伝わった時期は定かでないが、平安時代には栽培をしていた説や
寛永年間(1624年〜)に中国から渡来したとの説もあります。
果実の外観は緑色に深い緑色の縦縞が入ったものが一般的であるが、
薄緑色のものや黒に近い深緑色のものもある。
果肉の色は赤もしくは黄色。大玉の品種で糖度は11〜13度程度。
果実中心及び種子周辺の果肉の糖度が最も高い。
また、装飾・贈答用に特製のケースに入れて栽培した四角いスイカや、
異常に巨大に成長した物なども販売されて好評を博している。
ただし、値段は通常のスイカの5〜10倍程度であり、庶民が簡単に買える物
ではないということも事実である。
また、味も大味になりがちとの説も存在する。
結局、庶民は食べられないので味は不明・・・・。
スイカの成分
ウォーターメロンとも呼ばれるスイカは、可食部(食用にするところ)
の90%以上は水分で、果汁中には糖質7.9%と、その他様々な成分を含み
ます。また、果肉・果汁の紅色の色素はリコピンとカロチンの混合物です。
主に注目されている成分にリコピン、カリウム、シトルリンと三つあり、
もちろんこの他にもたくさんのビタミンやミネラルが豊富に含まれていま
す。主な成分を紹介していきましょう。
リコピン
トマトに含まれる赤い色素と同じもので、赤玉スイカの赤い果肉に含まれ、
活性酸素を消去してくれる抗酸化作用があります。
活性酸素は、普段細菌などを攻撃している物質ですが、大量に発生すると
体内の攻撃をし始め、動脈硬化やガンや老化を促進すると言われています。
スイカに含まれるリコピンには、活性酸素を抑える抗酸化作用があり、
活性酸素の攻撃が始まってもリコピンがそれを沈静化し、攻撃から守って
くれます。この抗酸化作用は、これまでのガンに良いと言われていた
β−カロチンの2倍もあると言われています。 スイカはトマトの1.5倍の
量を含みます。
カリウム
ミネラルの一つで、体の中のいらない塩分を尿の中へ出す働きを持ちます。
シトルリン
最近注目されはじめた成分で、アミノ酸の一つに挙げられます。
他の果実にはほとんど見られない成分で、スイカにはこれが含まれています。
体内に吸収されると、老廃物や、有害物質などを体外に出してくれる利
尿作用があります。
カリウム+シトルリンの働きで、スイカを食べると利尿作用が高まり、
腎臓の働きを正常にするのです。その結果としてむくみをとり、
腎臓病、膀胱炎、高血圧の予防などに効果が期待されるのです。
※ただし、腎臓・肝臓に疾患のある人、糖尿病の人などで、食べ物に制限
のある人は医師の指示に従ってください。
シスペイン
この成分はビタミンCの酸化や破壊を防止する作用があるそうです。
お肌のシミ・ソバカス対策としての効果もあるみたいです。
イノシトール
ビタミンB群でもあるイノシトールには、動脈硬化を防ぐ他に、甲脂肪肝
ビタミンと呼ばれるように、肝臓に脂肪がつかないようにする働きもあります。
マンノシターゼ
ダイエットで注目されている成分で、糖質分解酵素です。
グルタチオン
グルタチオンには、解毒を司る肝機能を高める作用があります。
グルタチオンは、アミノ酸の一種(グルタミン酸、システイン、グリシン
から成るトリペプチド)で、有害物質を体内で解毒する肝臓の機能を強化する
作用が認められています。
ただし、これらの有効成分には様々な機能性が期待されているとはいえ、
食品としてのスイカをどれだけ食べれば効果がでるというものではありま
せんので、過剰な期待はしないようにしましょう。
最後に・・・
スイカは実は秋の季語としても用いられる。
これはスイカの旬が立秋(8月7日頃)を過ぎる頃であるからで、
この時期は暦の定義では秋になり、秋の季語として使われるわけである。
暦上は秋ですが、この時期はやはり夏!
夏の風物詩の一つとして、旬のスイカを食べることで、夏バテ対策や
水分補給をしっかりと行っていきたいものです。